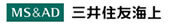暦年贈与の落とし穴
1.はじめに
2015年1月1日以後に発生した相続から、相続税の申告が必要となるボーダーラインが引き下げられ、相続税の申告を行った人が増えています。ボーダーライン引き下げ前の2014年における、死亡者数に対する相続税の申告書を提出した件数の割合は4.4%でした。直近のデータである2017年は8.3%と倍増しています。
相続対策として従来から生前贈与が行われてきましたが、適切に行わないと相続税が加算される場合があります。
今回は1年間の生前贈与に課税される「暦年贈与」に焦点を当て、対策を行う際の留意点について解説します。
2.暦年贈与とは
暦年贈与とは、1月1日~12月31日までの期間で生前贈与を受けた資産について、受贈者に贈与税を課すものをいいます。暦年贈与のもとでは、1年間に生前贈与を受けた資産の評価額が110万円(基礎控除)までであれば、贈与税は課税されません。贈与税は、課税価格から110万円を差し引いた金額に、所定の税率を乗じて算出します。税率は基礎控除後の課税価格に応じて、10%から55%まで8段階となっています。父母・祖父母から生前贈与を受けた人がその年の1月1日において20歳以上である場合、基礎控除後の課税価格が300万円を超えるケースで贈与税の負担が軽くなるように配慮されています。
3.暦年贈与の効果
暦年贈与を複数回行うことによって贈与者の財産が減少し、贈与者が死亡した時に相続税が軽減されたり、またはゼロとすることができる効果があります。前述のように、近年相続税の申告が必要になる可能性が高くなってきたことから、暦年贈与を行って相続対策を行う意向も高まってきています。相続税がかからないような人でも、自分の子や孫に自分自身の資金を有効に使ってもらおうと、一定額の現金を暦年贈与するケースもよく見られます。
その際に、思いがけなく多額の贈与税が課されたり、相続対策が対策にならなったりする「落とし穴」があります。贈与者が死亡して、その後相続税の申告を行った後に税務署から税務調査が入り、申告内容の修正を求められ、相続税を追徴されたりする場合があるのです。
4.贈与と認められないケース
父母・祖父母が子の名義の口座に一方的に振り込みを行っているケースがあります。受贈者が「もらいます」という意思表示をしていなければ、贈与契約とみなされません。このようなケースでは、贈与者が自分の資産を意図的に少なくするために子や孫の口座に現金を移しているとみなされ、結果的に相続財産が減らないことになります。
また、子や孫に贈与の認識があっても、その口座の預貯金通帳・印鑑・キャッシュカードを贈与者である父母・祖父母が管理していれば、子や孫は自由にその資金を使えないので、贈与とみなされない可能性があります。
贈与者・受贈者両者が署名・押印した贈与契約書を作成しておきましょう。公証役場で確定日付を得ておくことが望ましいと言えます。その上で子・孫自身が管理している口座に振り込んで、記録を残しておくことが肝要です。
5.基礎控除内の贈与と認められないケース
1回の贈与額が基礎控除の110万円以内となっていても、まとまった金額を複数の年に分割して贈与しているとみなされれば、「連年贈与」とみなされます。この場合、最初の年に一定の算式で算出された「定期金の受給権」が贈与税の対象となり、多額の贈与税が課せられることがあります。連年贈与とならないように、前述のような贈与契約書を毎年締結する等、基礎控除内の暦年贈与と認めてもらえるようにしておくことが重要です。
6.相続対策にならないケース
相続開始の3年以内に相続人が暦年贈与を受けた財産は、相続財産に加算されてしまいます。死亡する直前に暦年贈与を行っても、相続対策になりません。暦年贈与を行う場合は、長い期間をかけて行う必要があります。
ただし、孫等のように相続人ではない人が相続開始3年以内に贈与を受けた財産は、相続財産に加算されません。したがって、対策できる期間に余裕が持てない可能性がある場合は、相続人以外の人に贈与を行ったり、住宅資金の贈与や教育資金の一括資金の贈与等、別の生前贈与の制度を組み合わせる対策が必要です。
7.さいごに
自分自身の財産を配偶者が相続した後、その配偶者に相続が発生した時の相続税の納税資金の準備や、財産分割を円満に行うことを目的(いわゆる二次相続対策)として、その配偶者を被保険者とする生命保険に加入する対策の方法があります。その際、保険料相当額の現金を毎年配偶者に贈与し、配偶者はそれを毎年の保険料に充当する選択肢があります。
生前贈与を活用した相続対策を行う場合は、必ず税理士やファイナンシャル・プランナー等の専門家に相談しましょう。